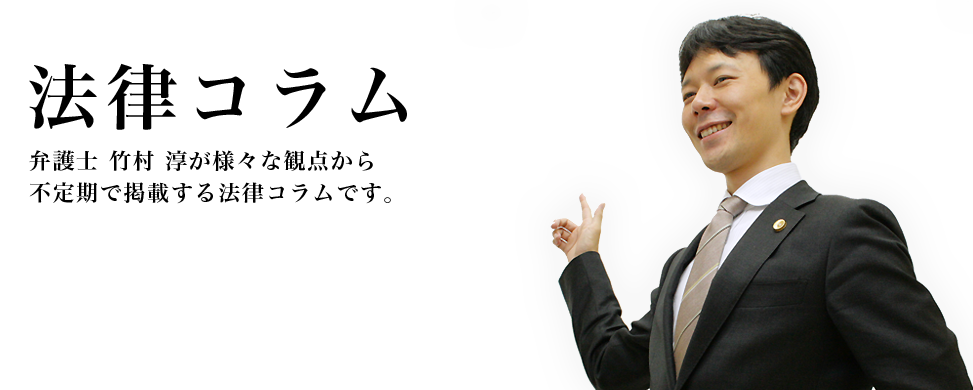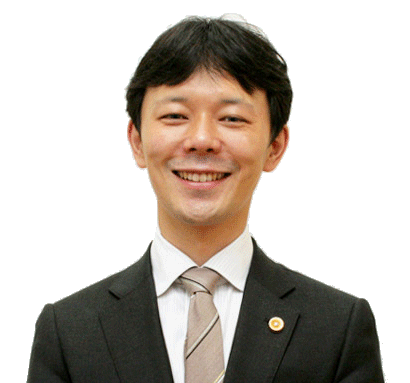1.自筆証書遺言について①(自書の要件)
民法968条によれば、自筆証書遺言は「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し」なければならないとされています。
したがって、ワープロ等で作成されたものは、無効となってしまいます。
では、手が震えるなどするため文字を書くことが困難な者が他人の添え手による補助を受けて遺言を作成した場合、「自書」したといえるのでしょうか。
この点につき、最高裁(昭和62年10月8日判決)は、自筆証書遺言は他の方式の遺言と異なり証人や立会人の立会を要しないなど、最も簡易な方式の遺言であり、それだけに偽造、変造の危険が最も大きく、遺言者の真意に出たものであるか否かをめぐつて紛争の生じやすい遺言方式であるといえるから、「自書」の要件については厳格な解釈をするべきとしたうえで、病気その他の理由により他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、
① 遺言者が証書作成時に自書能力(遺言者が文字を知り、かつ、これを筆記する能力)を有すること、
② 他人の添え手が、単に始筆もしくは改行にあたり、もしくは、字の間配りや行間を整えるため、遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、または、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであること、
③ 添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できること、
が認められる場合には有効であるとの判断を示しました。
したがって、結論としては、他人の添え手による補助を受けて遺言を受けて遺言を作成した場合であっても「自書」の要件を満たす場合があるということになります。
しかし、後々の紛争を回避するという観点からは、文字を書くことに他人の補助が必要なのであれば、自筆証書遺言ではない遺言の方式、具体的には、公正証書遺言を作成するべきと考えます。
2.自筆証書遺言について②(日付の要件)
民法968条によれば、自筆証書遺言は「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し」なければならないとされています。
この日付とは、特定の年月日のことをいい、年月の記載はあるが日の記載がないときは無効です(最高裁・昭和52年11月29日判決)。
では、「●年●月吉日」と記載した場合はどうでしょうか。
最高裁によれば、このような記載では特定の日を表示したものとはいえず、無効となります(最高裁・昭和54年5月31日判決)。
3.自筆証書遺言について③(押印の要件)
民法968条によれば、自筆証書遺言には「押印」が必要とされています。
A.この押印はどのような印鑑を用いればいいのでしょうか。実印でなければならないのでしょうか。
Q.この点については、実印である必要はなく、認印でも構わないとされています。それどころか、判例によれば、印鑑を用いる必要すらなく、指印でも足りるとされています(最高裁・平成元年2月16日判決)。
A.では、押印はどこにする必要があるのでしょうか。
Q.この点については、特に制限は無く、遺言書本文の入れられた封筒の封じ目にされた押印でも有効とした判例があります(最高裁・平成6年6月24日判決)。
4.まとめ
遺言書(自筆証書遺言)は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印が必要です。
とはいえ、手軽に書けるので自己判断で作成すると、無効及びトラブルの原因になるリスクがあります。
リスクを避け、正しい遺言書(自筆証書遺言)を作成するためには、弁護士等の相続の専門家に相談しながら作成する事をおススメします。
関連記事
遺言書(自筆証書遺言)を書く上での注意点
1.自筆証書遺言について①(自書の要件) 民法968条によれば、自筆証書遺言は「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し」なければならないとされています。 したがって、ワープロ等で作成されたものは、無効となってしまいます
生命保険金の相続 遺産分割対象になるのか?
1.生命保険金と遺産分割①(遺産該当性) 被相続人Xには、相続人として妻Aと子Bがいるものとします。 Xは、生前、生命保険に加入しており、Aを死亡保険金の受取人としていました。Xが死亡したので、保険会社からAに死亡保険金
遺言の検認当日の流れ(東京家庭裁判所の場合)
遺言の検認当日の流れ(東京家庭裁判所の場合) 自筆で書いた遺言の場合、原則として、裁判所での検認手続きが必要となります(民法1004条)。この検認手続きが必要ということは、いろいろな方がインターネット上で書いていますが、
Last Updated on 2025年3月19日 by takemura_jun