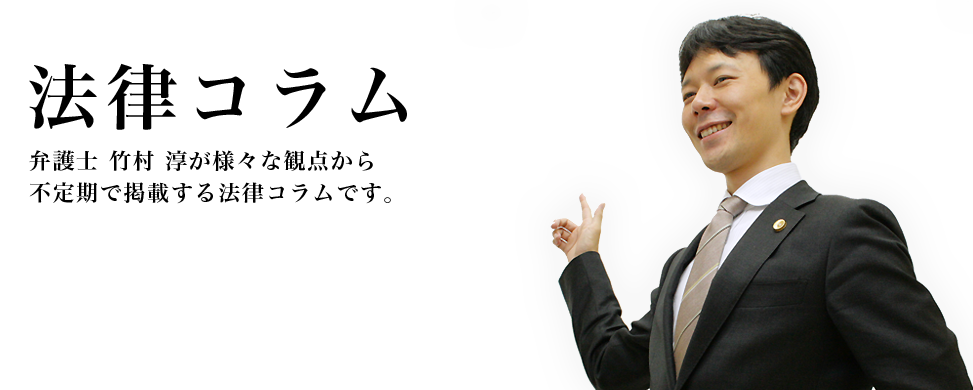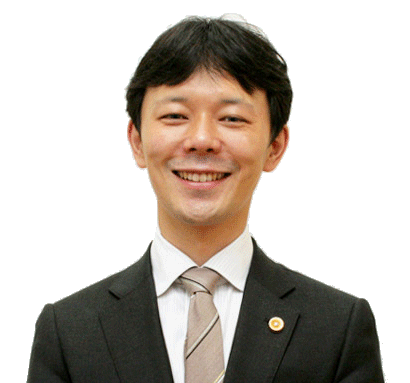1.所定労働時間と法定労働時間の違い
所定労働時間とは、企業が就業規則や労働契約で定める労働時間のことであり、法定労働時間の範囲内で設定される必要があります。
一方、法定労働時間とは、労働基準法により定められた労働時間の上限(1日8時間、週40時間)をいいます。
2.時間外労働
時間外労働とは、所定労働時間を超えて労働させることをいい、法定時間外労働と法内時間外労働があります。
法定時間外労働とは、法定労働時間を超えて行う労働のことであり、法内時間外労働とは、所定労働時間が法定労働時間よりも短く設定されている場合に、所定労働時間を超えて法定労働時間の範囲内で行う労働のことをいいます。
例えば、企業が1日7時間の所定労働時間を設定した場合で、8時間を超えて労働したときは、1時間は法内時間外労働、それを超える時間は法定時間外労働となります。
36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)
労働基準法では、原則として法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働をさせることはできません。しかし、企業が法定労働時間を超えて労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合、労働基準法第36条に基づき「36協定(サブロク協定)」を締結し、行政官庁に届出をする必要があります。
36協定の要点
- 労働組合または労働者の代表と使用者との間で締結する。
- 法定労働時間を超える労働時間の上限を定める。
- 36協定の締結がない場合、法定時間を超える労働は違法となる。
- 労働時間の延長上限(原則として月45時間・年360時間)が定められており、特別条項を適用する場合でも一定の上限規制がある。
36協定は、長時間労働の抑制と労働者の健康を守るために重要な役割を果たします。
3.労働時間の原則(法定労働時間)
労働基準法では、使用者は労働者に休憩時間を除き「1日8時間、1週40時間」を超えて労働させてはならないと定められています(法定労働時間 労基法32条)。
就業規則等で、所定労働時間を1日10時間と定めたとしても、8時間を超える2時間部分は無効となります。
労働組合または労働者の代表者との間で協定(いわゆる「サブロク協定」)を締結し行政官庁に届出をした場合は、法定労働時間を超えて労働させることができますが(労基法36条)、法定労働時間を超える労働時間については、割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条)。
ただし、労働者が常時10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については、特例措置対象事業場とされ、「1週44時間までの労働が認められる」という例外規定があります。
4.労働時間について(休憩時間)
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされています(労基法34条1項)。
ここでいう労働時間とは、実労働時間のことを指します。
使用者は、休憩時間を自由に利用させなければなりません(労基法34条3項)。
では、使用者は、休憩時間につきいかなる規制をすることも許されないのでしょうか?
この点につき、最高裁は、休憩時間の自由とは時間を自由に利用することが認められたものにすぎず、休憩時間の自由利用が企業施設内で行われる場合は、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使による制約を免れることはできず、また、従業員は、労働契約上、企業秩序を維持するための規律に従うべき義務があるため、休憩時間は、労務提供とそれに直接附随する職場規律に基づく制約は受けないが、これ以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れないとしています(最高裁・昭和52年12月13日判決)。
この判例は、休憩時間自由利用の原則も一定の制約を受ける場合があることを示したものですが、原則は、休憩時間は自由に利用できるのであり、そして、労働者が自由に利用できる休憩時間を確保することは、適切な労働環境の維持と労働者の権利を守るうえで不可欠であることは認識すべきでしょう。
5.法定労働時間、法定休日労働、法内時間外労働、法定外休日労働の区別
法定労働時間
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限(1日8時間、週40時間)を指します。
法定休日労働
法定休日労働とは、法定休日に労働することを指し、通常の賃金に対して35%以上の割増賃金の支払い義務はあります。
法内時間外労働
法内時間外労働とは、所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合に、所定労働時間を超えて法定労働時間の範囲内で行われる労働のことをいいます。例えば、所定労働時間が7時間である場合、7時間を超え8時間までの労働がこれに該当します。
割増賃金の支払い義務はありません。
法定外休日労働
法定外休日労働とは、所定休日が法定休日よりも多く設定されている場合に、法定休日ではない日に行われる労働のことをいいます。例えば、土日週休2日制で、法定休日が日曜日と定められている場合に土曜日に行われる労働がこれに該当します。
割増賃金の支払い義務はありません。
ただし、法定外休日労働については、これによって労働時間が週40時間を超えた場合は、40時間を超える部分につき、割増賃金が発生することになります。
6.通勤時間は労基法上の労働時間に該当するか?
通勤時間は、労働力の提供という債務を履行するための準備行為であって、使用者の指揮命令下に入る前の段階の行為ですので、労働時間には該当しないと考えられています。
では、一旦会社に立ち寄ったあと、現場に移動する場合、会社から現場に移動するまでの時間は労働時間に該当するのでしょうか。
これについては、会社に立ち寄ったときにいかなることが行われているかによって、判断が変わってくると考えられます。
すなわち、会社に立ち寄っても、点呼や打ち合わせ等が行われず、現場までの移動方法につき会社の指示が無いような場合は、通勤時間の延長と評価しうるので、労働時間に該当しないという判断になるでしょうし、逆に、会社で点呼や打ち合わせが行われ、そこで当日入る現場が決められるというような場合であれば、会社に立ち寄った時点で会社の指揮命令下に入ったといえ、労働時間に該当するという判断になると思われます。
まとめ
所定労働時間を設定する際は、労働基準法で定められた法定労働時間や休憩時間の規定を遵守することが重要です。また、労働時間の種類の区別を正しく理解し、適切な対応を取ることで、労働者の健康と労働環境の適正化を図ることができます。
本記事を読むことで、所定労働時間や労働時間の考え方についての疑問が解決し、適切な労務管理の参考になれば幸いです。
Last Updated on 2025年3月19日 by takemura_jun