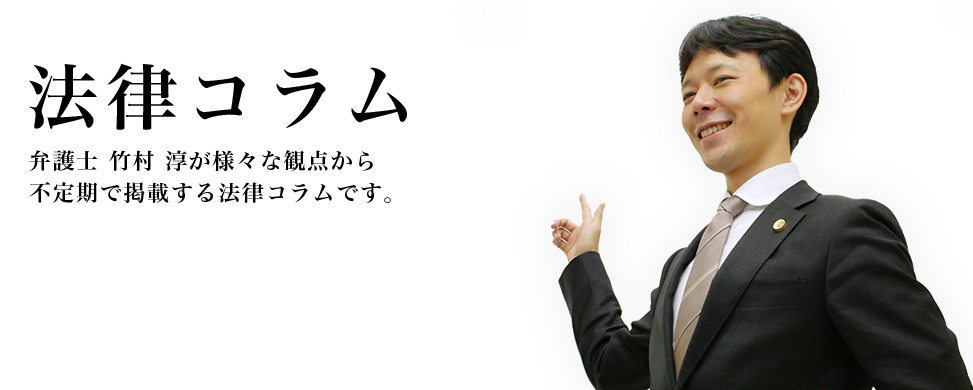
弁護士法律コラム一覧
目次
弁護士コラム
速報:強制わいせつ罪の成立に性的意図は不要(最高裁平成29年11月29日判決)
強制わいせつ罪の成立に性的意図は不要(最高裁平成29年11月29日判決) 最高裁は、昭和45年に強制わいせつ罪の成立要件として、その行為が犯人の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図が必要との見解を示しました。
長期間の経過と民法597条2項但書の適用(最高裁平成11年2月25日判決)
長期間の経過と民法597条2項但書の適用(最高裁平成11年2月25日判決) 1.事案の概要 昭和33年12月頃、X社の代表取締役はAであり、Aの長男であるBと次男であるYはX社の取締役であった。 AはX社が所有する土
市川市市長選挙の再選挙について(公職選挙法)
市川市市長選挙の再選挙について(公職選挙法) 平成29年11月26日実施の千葉県市川市の市長選挙は、再選挙が実施されることになりました。 これは、公職選挙法が、地方公共団体の長の選挙については、有効投票の最多数を得ただけ
強制わいせつ罪の成立と性的意図
強制わいせつ罪の成立と性的意図 強制わいせつ罪について規定する刑法176条は「十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為を
平成29年10月22日実施の最高裁裁判官国民審査の参考情報
平成29年10月22日実施の最高裁裁判官国民審査の参考情報。 平成29年10月22日に実施される最高裁裁判官の国民審査の対象となる最高裁の裁判官は、大谷直人、小池裕、木澤克之、菅野博之、山口厚、戸倉三郎、林景一の7名の裁
最高裁裁判官国民審査とは
憲法79条2項は「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする」と規定します。 これ
契約書関連
不動産・賃貸借関連
定期借家契約とは?②(成立要件)
定期借家契約は明確に期限を区切って物件を貸すことを可能にする制度ですが(普通借家契約との違いは前述)、定期借家契約を締結するためには一定の要件を満たす必要があります。 まず、定期借家契約を締結する場合は、普通借家契約とは
賃借人の自殺による損害賠償責任
賃借人は、目的物を善良な管理者の注意をもって使用収益する義務(善管注意義務)を負っています。 では、物件内において自殺しないようにすることがこの義務の内容に含まれるのでしょうか。 近時の裁判例では、物件内部において賃借人
定期借家契約とは?①(普通賃貸借契約との違い)
「分譲マンションを所有しているが、2年間転勤することになったので、その期間だけ貸したい」 このようなニーズがある場合、定期賃貸借制度の利用を検討するべきです。 定期借家契約とは、書面により賃貸借契約書を締結する等の一定の
相続・遺言関連
労務・労基関連
非公開会社である取締役会設置会社において代表取締役を株主総会の決議により選任することの可否(肯定)(最決平成29年2月21日)
非公開会社である取締役会設置会社において代表取締役を株主総会の決議により選任することの可否(肯定)(最決平成29年2月21日) 会社法は「取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項
秘密保持義務違反と違約金
【秘密保持義務違反と違約金】 従業員に対し雇用契約あるいは就業規則により秘密保持義務を課している会社は多いのではないかと思います。 しかし、秘密保持義務違反があった場合であっても、当該従業員に対し損害賠償請求をするために
パワーハラスメントの裁判例
1.福岡高判平20.8.25判時2032号52頁 海上自衛隊で上官が「お前三曹だろう、三曹らしい仕事をしろよ。お前は覚えが悪いな。バカかお前は、三曹失格だ」等の発言をしたという事案(パワハラを受けた自衛官は護衛艦内で自殺
年次有給休暇の時季指定権行使の時期
判例は、労基法39条の年次有給休暇の権利は、労基法上の要件が満たされることによって当然に発生する「年休権」と、有給休暇を取得する時季を指定する「時季指定権」の2つによって構成されるとの立場をとっています(最高裁・昭和48
年次有給休暇(労基法39条)の法的性質
労基法39条1項は、使用者は、一定の要件を満たした労働者に対し、有給休暇を「与えなければならない」と規定していますが、同条5項は、使用者は、有給休暇を「労働者の請求する時季に与えなければならない」と規定しています。 この
注目労働裁判例・大阪高判平成28年7月26日(労契法20条の「不合理と認められるもの」―ハマキョウレックス事件)②
本事件の最高裁判決について記事を書きました。こちらをご覧ください。 平成28年7月26日の大阪高等裁判所の判決の概要は以下のとおりです(事実関係及び原審の判断はこちらをご参照ください)。 1 正社員と契約社員との間の賃金
個人情報保護関連
民泊関連
contact
まずは法律相談にお越しください
法律相談は有料ですが、資力のない方は法律相談料の負担がなくなる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
